学会誌
 学会誌
学会誌
『民俗芸能研究』 バックナンバー
バックナンバー 論文二次使用願
論文二次使用願
 入会のご案内
入会のご案内
 入会申込書
入会申込書
⇒(PDF形式)
⇒(Word形式)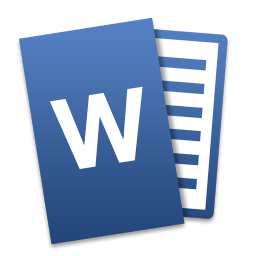
過去の『民俗芸能研究』一覧 [2024/12/03 更新]
第13号目次(平成3年5月)
【論考】
春日杜における神楽祭祀とその組織 岩田 勝
修験の延年芸能 山路 興造
【報告】
秋田県鳥海町の本海流獅子舞 ― 十三講中におげる獅子舞の構成 ― 山本 宏子
芸能と地域社会 菊池 一成
第12号目次(平成2年11月)
【報告】
三河大神楽における生まれ清まり 村松 貞義
【研究ノート】― 民俗芸能の舞台上演をめぐって ―
フィールドからステージヘの文化変容 山本 宏子
奇妙な舞台・徴妙な舞台 ― 民俗芸能大会と民俗芸能研究者 ― 笹原 亮二
全国民俗芸能大会私見 山路 興造
民俗芸能の公開論の進展のために 鹿谷 勲
民俗芸能大会雑感 佛坂 勝男
民俗芸能大会について 尾島 利雄
【研究動向】
永田 衡吉 の足跡 後藤 淑
民俗芸能誌の刊行と永田 衡吉 先生 中藤 政文
【書評】
岩田 勝 編『中国地方神楽祭文集』 鈴木 正崇
小川 学夫『歌謡(うた)の民俗 奄美の歌掛け』 久万田 晋
久下 隆史『村落祭祀と芸能』 山路 興造
民俗芸能研究文献目録 平成元年 渡辺 伸夫 編
第11号目次(平成2年5月)
【論考】
八月踊りの始源 ― 奄美大和村の事例から ― 大石 泰夫
「弟子座」の形成 ― 地域の宗教感性と芸能への身体動機 ― 森尻 純夫
【報告】
近代の農村における人形浄璃璃 ― 京都府下の事例を中心として ― 池田 淳
奄美大島笠利町宇宿の八月踊り 内田 敦
【書評】
本田 安次 著『伊勢神楽歌考』 岩田 勝
第10号目次(平成元年11月)
【論考】
雨乞踊りと八幡信仰 大森 惠子
文化としての民俗芸能研究 橋本 裕之
【報告】
大債内野口伝斎部流鴨沢神楽の概要
― 第1報 幻の大償斎部流野口家流式神楽 ― 大阿久 国賢
【研究動向】
最近の各地の民俗芸能研究書 山路 興造
【書評】
『中世の民衆と芸能』『近世の民衆と芸能』 武井 正弘
『和舞・杜伝神楽の伝承並びに比較調査報告書』 武井 正弘
高橋 春子 編『民俗と衣裳』 森尻 純夫
守屋 毅 編『大系 仏教と日本人』7 西瀬 英紀
民俗芸能研究文献目録 昭和63年 渡辺 伸夫 編
第9号目次(平成元年5月)
【論考】
「松かげ」考 本田 安次
〈花祭〉と天狗伝承 ― 招かれざる精霊たちの座 ― 上野 誠
霜月祭りの湯立 ― 天龍村・富山村の事例から ― 板谷 徹
役舞の世界 ― 陸中沿岸地方の神楽より ― 神田 より子
「審神者」考 岩田 勝
【報告】
山口県の荒神神楽 ― 新南陽市三作岩戸神楽舞を中心として ― 財前 司一
第8号目次(昭和63年11月)
【論考】
萬歳の成立 山路 興造
霜月神楽に残る猿楽芸の一例 ― 御神楽祭りの後戸の神 ― 山﨑 一司
【資料】
今田人形座年表 伊藤 善夫
【研究ノート】― 民俗芸能研究の方法をめぐって 1 ―
芸能伝承の目的 井口 樹生
民俗芸能の構造と杜会構造 山本 宏子
民俗としての芸能 ― その研究視点を考える ― 茂木 栄
【書評と紹介】
『御柱祭と諏訪大杜』 武井 正弘
三隅 治雄『民俗芸能の芸』 森尻 純夫
山﨑 一司『隠れ里の祭り』 須藤 功
守屋 毅 編『祭りは神々のパフォーマンス』 髙山 茂
民俗芸能研究文献目録 昭和62年 渡辺 伸夫 編
第7号目次(昭和63年5月)
【昭和62年度大会公演】
神楽と能と 本田 安次
【論考】
祭儀と芸能のあいだ ― 芸能研究方法論序説 ― 岩田 勝
盛岡藩の操師鈴江四郎兵衛と淡路人形 門屋 光昭
【報告】
中国ヤオ族の盤王祭の舞踊 ― 神楽との異同 ― 星野 紘
お問い合わせ先
- 民俗芸能学会事務局(毎週火曜日 午後1時~4時)
- 〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1 早稲田大学演劇博物館内 [地図]
- 電話:03-3208-0325(直通)
- Mail:office[at]minzokugeino.com (* [at] を @ に換えてお送り下さい。)